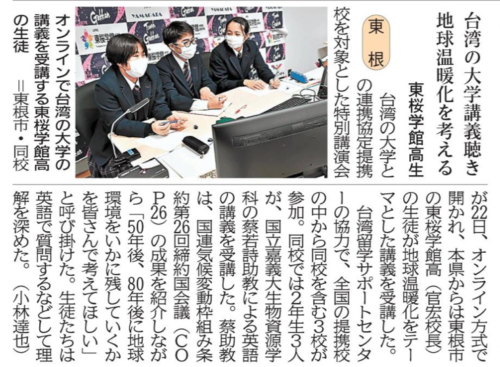令和3年度第19回斎藤茂吉ジュニア短歌コンクール(中学校の部)において、中学3年藤平恭子さんが、最優秀賞に輝きました。おめでとうございました。
なお、最優秀賞の表彰式は、令和4年5月15日(日)開催予定の生誕140年第48回斎藤茂吉記念全国大会の席上にて執り行う予定となっているとのことです。
「斎藤茂吉ジュニア短歌コンクール(中学校の部)」最優秀賞 中学3年 藤平恭子さん
はんこ屋の祖父が片手で彫りゆくはキラリと光る「恭賀新年」
また、次の皆さんの作品が優秀作品等に選ばれました。
【優秀作品】
中学1年 星川美月さん 「テキストを泳ぐ赤文字青丸はくやしい思いと『分かった』の跡」
【入選作品】
中学1年 西尾奏人さん 「東京の友から届いたLINEには変わらぬ笑顔真っ赤なリンゴ」
中学2年 寒河江陸さん 「おおみそかおしゃれに飾るかむやしろ除夜の鐘鳴りあふれる笑顔」
高校1年 保科早絵子さん 「もう少しあと3文字を書ききればその時響く『終了』の声」
高校2年 奥山知佳子さん 「目の前に広がる雪のキャンパスに踏み出しつける私の足跡」
高校2年 工藤みなみさん 「年明けて進路に悩む深夜二時部屋から見えぬ北斗七星」
高校2年 佐々木優和さん 「雪灯篭狭く長い道照らし目指す先には鐘の鳴る音」
高校2年 山川日菜季さん 「今せむといひしばかりに大量の宿題の山をながめつるかな」