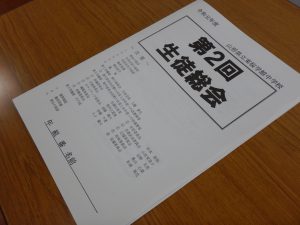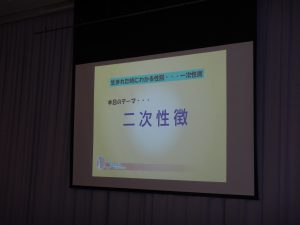山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
日常の生活や自分自身を見つめた絵画作品が、この度上記の展覧会で受賞を果たしました。それぞれの思いが、絵筆を通してのびのびと表現されています。
特選 中学1年 原田 未森さん 「新たなる希望」(上段右)
特選 中学3年 尾崎 杏華さん 「海の底から」(下段右)
入選 中学1年 奥山 瑛太さん 「闇をも飲み込め!!俺の情熱!!」(上段左)
入選 中学2年 近藤 和華さん 「愛でつながれ」(下段左)




山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
1月22日(水)の部活動の時間に、本校中学美術部員が、「MINIATURE LIFE展」を鑑賞する活動を行いました。この展覧会は、1月11日(土)から「まなびあテラス」にて開催されているもので、ミニチュア写真家で見立て作家の田中達也さんの作品展となっています。日常の何気ないものが、ジオラマ人形とユーモアあふれる田中さんの作品タイトルとの融合で、ものの見方に新たな発見をもたらしてくれます。「アートで地域を笑顔にする活動を」をコンセプトに、常にアートの可能性を模索している我が校の美術部にとって、今回の鑑賞会は、とても楽しく新たな刺激を頂いた鑑賞活動となりました。




山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
百人一首かるた大会が開催されました。1チーム7人~9人の中から5人が選抜され、80チーム、総勢400人が同時にかるた競技を行います。次の札が読まれる太鼓が鳴り響くと、真剣なまなざしと静寂が訪れピリピリした雰囲気になります。放送部の読み手が札を読み始めた瞬間に多くの生徒たちが反応し、かるたを取った生徒は勝ち誇った顔、そして笑顔です。静と動、それがこのかるた大会の醍醐味かもしれません。多くの生徒たちが、疲れた・・・でも、楽しかった・・・。充実した時間を過ごしたようでした。








山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
1月16日(木)に、さとこ女性クリニック院長の井上聡子先生を講師にお招きし、第1学年の健康コンパス「いのちの学習」を行いました。二次性徴における体や心の変化を詳しく、そしてわかり易くお話しいただきました。自分の命、大切な人の命を守るために、正しい知識を身に付け、適切な判断ができるようにしていきましょう。

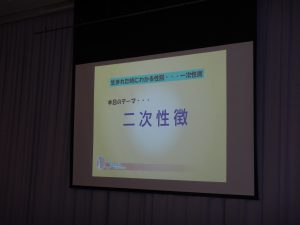
山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
1月9日(木)のAT(アクティブタイム)は「学び合いタイム」を行いました。今回の「学び合いタイム」は、21日(火)に中高合同で行われる百人一首かるた大会に向けての取り組みを行いました。百人一首かるた大会は、楯岡高校から続いている歴史と伝統のある本校の特徴的な行事です。1年生は初めての大会となるため、2年生や3年生からコツや覚え方などを教えてもらいながら、理解を深めました。




山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
本日23日(月)、中学校の2学期終業式が行われました。
今回の校長先生の式辞では、「2学期大きな事故もなく、概ね生徒全員が健康に過ごせたこと」と「安全で安心して生活できるように一人ひとりが心がけてくれたこと」、「一人一人がかけがえのない存在であり、自分自身を大切にすることはもちろん、家族や友人など周囲の人たちも大切に思う気持ちを持ってほしい」との話がありました。また、「計画された偶発性理論」というキャリアに関する理論に触れ、「個人のキャリアの8割は予想しない偶発的なことによって決定される」と言われているが、「好奇心」「持続性」「楽観性」「柔軟性」「冒険心」の5つの行動指針が大切であること、そして、「思考を変えれば、言葉が変わる。言葉が変われば、行動が変わる。行動が変われば、習慣が変わる。習慣が変われば、性格(人格)が変わる。性格(人格)が変われば、運命が変わる。」という言葉を紹介してくださいました。



山形県立 東桜学館 中学校・高等学校