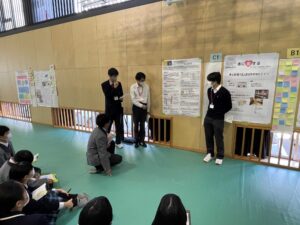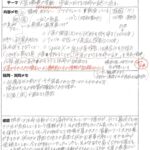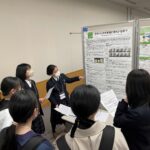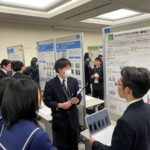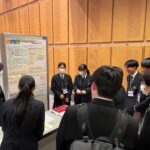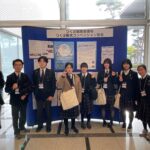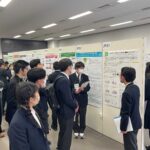令和6年3月14日から15日の日程で、つくばサイエンスツアーが実施されました。
理系を選択した生徒80名と引率教員3名で、3つのコースに分かれて様々な研究施設を訪問しました。以下、生徒の感想をお伝えします。




高エネルギー加速器研究機構
・エネルギーを加速させて放射線の実験をする機会を実際に見た。色の違いは波長の違いであり、赤外線や紫外線の構造の違いも初めて知ることができた。宇宙からの放射線を実際に目で確認したり研究の様子を伺ったりすることができてとても興味深かった。
・エネルギーのことやそのエネルギーが人体に及ぼす影響が本物の論文とともに示されていた。それを確かめるための器具などもたくさんあって、体験しながら学ぶことができた。
JAXA
・よく映像で見るものを間近で見ることができ、想像を超えるスケールの大きさに圧倒された。また宇宙で重力ありと無重力状態での違いを利用し、マウスの骨密度を比べる実験の結果ガおもしろいと思った。そこから医薬品の開発がされていくのも高齢化が進む現代に合っているなと思った。
・機内観察や実際に働いている管制室の様子がとても面白かった。宇宙飛行士の選抜試験のための場所の見学も面白かった。閉鎖環境適応訓練では、英語力や健康を測るが、特に協調性を見ると知って宇宙飛行士に関心を持った。宇宙兄弟をもう一度読みたくなった。
・普段の生活で見る機会のない服、道具を間近で見ることができ、宇宙開発の可能性と、ミスが許さなれない場を扱っていることに偉大さをかんじた。私もミス出来ないところでしないという確かな技術力と精神をみにつけていきたい。
防災科学研究所
・地震をおこす機会やプレートの摩擦、豪雨を再現する機会を間近で見ることができた。一時間あたり300mlという、ゲリラ豪雨と同じ量の雨を降らせることができるということに驚いた。また、椅子の上で振動7の地震を実際に体験した。短時間で収まったが、揺れがかなり激しく不規則的だったため、椅子の上でも体勢を保つのに必死だった。また、その夜実際に福岡で地震がおこり、防災科研のサイトを見て情報を得ることができた。
・家屋倒壊や地震発生のメカニズムを解明し、災害発生時の対応の仕方や被害の縮小のために研究していることが分かった。非常食や水などの準備は災害が起こってからでは遅いため、このツアーを機に普段から備えようと思った。
理化学研究所
・ツアーを通して感じたことは、人間の生活の質の向上とともに、環境など他の影響を害さないものを求めて道具を作る必要があるということだ。わたしが特に良かったと感じた施設は理化学研究所で、預けてもらったリソースを培養、保管し研究者に提供するというシステムとその施設に感銘を受けたからであり、様々な専門分野の人が共同している現場であることを理解したからである。
サイエンス・スクエアつくば
・様々な日本の先端技術を見れた。臨床実験に使われるセラピーロボットや、コンゴの子どもたちを救うための戦略的都市鉱山など面白いものがたくさんあった。セラピー用ロボット「パロ」はアザラシの赤ちゃんの見た目をしている。それは、人間がよく飼育する見慣れた動物(犬や猫)だとどうしても使用者が動作に違和感を感じてしまうため、全く見たことのないアザラシの赤ちゃんにすることで、ロボットである違和感を軽減し、より一層セラピー効果をもたらすためだそうだ。
食と農の科学館
・農学部に対する印象が変わった。品種改良を行い、より美味しい作物を栽培するだけでなく、農家や防具、他分野の視点に立ち、日本の抱えている食糧問題に本気で取り組もうとする強い意志が感じられた。医学との関連もあり、興味深かった
実験植物園
・自分は自然が好きで植物についても調べたりしていたが、日本にいる植物のうち四分の一の植物が絶滅危惧種に登録されているというのは知らなかったし驚いたが、植物園のような大きな実験施設がそれらの対策を考えているので、自分にもできることがあれば協力したいと思った。また、自分も植物に関することに携わってみたいと思った。
・日本は絶滅危惧種が1900種あり、筑波実験植物園のような「知る・守る・伝える」人々が必要だと感じた。ハウスには見たことの無い植物園が沢山あった。私は、ハウスごとに温度や湿度が違うことがとても心に残っている。それぞれの植物をよく見てみると、表面がザラザラしているものやふわふわしているもの、形が珍しい植物が多くあって面白かった。花、茎、葉、実など同じものはなく、すべてに個性があってどうしてこんな形になったのか考えながら見るのも楽しかった。
森林総合研究所
・生物の授業で木の種類や気候帯などを詳しく習ってから初めて詳しい説明を聞いたので、樹木園を研究者の方と回って森林に関する知識が増えたと思う。
・陽樹林エリアの空気が澄んでいて、呼吸がとても気持ちが良かった。森林を探検するのは凄く楽しい。何時間でもいれるなと感じたのに、いた時間は少なく、惜しい気持ちがある。スギは基本本州〜九州に分布していると知った。冷温帯林に所属していた。クスノキは神社にもあるため、今度県内の神社に訪れた時にどんな木なのかを考えながら歩きたい。常緑樹はずっと葉が茂っているわけではなく定期的に葉を落とすというのも面白いと感じた。
ツムラ漢方記念館
・ツムラ漢方記念館は漢方の効果や医学の歴史が学べるので医学部志望の人は是非行ったほうがいいと思った。
・漢方を実際に使用したことがなかったけれど、たくさんの製造過程を経て、作られていることがわかった。また、成熟する前と後で使い道が変わったり、1つの植物の使う部分によって別の効果が生まれたりするところが興味深かった。実際に見て、触れて、話を聞いて、匂いを嗅いで五感を働かせながら理解を深めることが出来た。