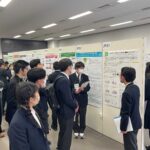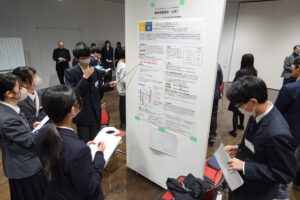3月26日(火)に東京農業大学世田谷キャンパスで、「ジュニア農芸化学会2024」という研究発表会において「セイタカアワダチソウの持つ毒性について」というテーマで、高校2年次生2名がポスター発表を行ってきました。この発表会は日本農芸化学会100周年記念事業の一環で実施され、全国の高校生が動植物や細菌類など生物にかかわるテーマでの発表を行う本格的な研究発表会となっています。動植物・細菌類・食品分野等の農芸化学分野を専門とする大学教授や大学院生から、今までとは違った視点でのアドバイスや大きな刺激をたくさんいただきました。今後に繋がる貴重な経験となりました。
【生徒の感想】
・外に発表をしに行くのは4回目のため、あまり緊張せずに発表することができた。今回の発表もたくさんの人からの助言や指摘をもらい新たに気づいたことや勉強になったことがたくさんあり、とても面白かった。また、全国の学校から集まった生徒の発表を聞いてみると、とてもレベルが高く、聞いていて感心する発表ばかりだった。このような発表会は幅広いジャンルの発表を聞いて興味を湧かせ、これからの日本の発展にも重要なものだと考えることができた。
・私はこれまで様々なところで研究発表の機会を得てきたが、今回のジュニア農芸化学会では全く触れられてこなかった点を数多く指摘され、ある程度厳しい意見をいただくことになるだろうとは思っていたが大変驚いた。その場ではどうにか対応できたものの、聞き慣れない用語が話に出たり考察の仕方を変えるべきだという助言をいただいたりと、農芸化学分野のスペシャリストだからこそできる視点だと感動した。いただいた意見や指摘はどれも欠陥を的確に突いたものであり納得できる一方で、今回で分かった課題を全て解決するのは非常に困難だと感じ、研究を仕事とする方々への尊敬がより深くなった。また、着眼点が面白いと評価してくださる方も多く、その点については自信になった。今回の経験は、正確な実験や検証をして可能性を多角的に考えた考察ができる力を身につけるための重要な糧になった。
2025-01-15T10:36:08+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
2024グローバルサミット”Be a Bridge”(山形県教育旅行誘致協議会主催)が台湾の高雄市で3月12日~13日に開催され、高校2年次から6名の生徒が参加してきました。本サミットには県内3つの高校から19名の高校生が参加し、6日間の日程で台湾へ渡航し、現地高校生との研究発表やディスカッションをメインの活動としながら、ホームステイやホストファミリーとの現地の観光などを通して国境を越えた交流を楽しみました。
1日目の研究発表では “The Impact of The Picture Superiority Effect on Vocabulary Acquisition”, “Junior High School Ethics Classes Using Context Shifting- An Approach to Enhance Intercultural Understanding -“と題して2つのグループが英語でプレゼンテーションを行いました。
また2日目に行われたディスカッションでは、SDGsの中からグループごとにテーマを選び、目標実現のためのアイディアを話し合い、まとめたものを英語で発表したようです。参加者からは「はじめはとても不安だったけど、実際行ってみると現地の学生と交流するのがとても楽しかった!」「お店などで日本語が通じることに驚いた。」などという感想が聞かれました。今回参加した生徒たちは、この経験を通して国際的なものの見方や考え方を養い、今後の学校生活や進路選択にも生かしてくれることと期待しています。
2025-01-16T11:48:55+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
3月4日に昆虫サイボーグの研究で知られるシンガポールの南洋理工大学(NTU)の佐藤 裕崇 教授(山形県出身)をお招きして,本校1年次を対象に国際理解講演会を実施しました。
佐藤 裕崇 教授は,世界で初めて昆虫とコンピュータを融合した「サイボーグ昆虫」を開発されました。サイボーグ昆虫は今後,災害現場での人命救助への活用が期待されています。今回の講演では「海外で勉強・研究・仕事をすること」をテーマに,サイボーグ昆虫をはじめ,海外での研究,仕事の取組みや,英語を学ぶことの大切さについてお話をいただきました。質疑応答の時間は次々と質問が飛び出し,たいへん有意義なやり取りがなされました。講演後も佐藤先生に質問する姿が見られ,生徒たちが大いに刺激を受けたことがわかりました。
講演を聞いた生徒からは,以下のような感想が寄せられました。
「研究の内容だけではなく,リアルな外国での学びについても教わることができ,新しい視点から進路を考える貴重な機会になりました。」
「佐藤先生がおっしゃっていた,新しいことに挑戦すれば批判がついてくるのは当然だという言葉が心にしみました。私も人に合わせて自分のしたいことを見失わないように,しっかりと自分を持って,やりたいことにどんどん挑戦していきたいと思いました。」
「『Superstar or Niche』というフレーズが心に残りました。どうしても,すごいことをしようとかスターになろうという気持ちを持ってしまいがちですが,今自分は何を持っているのか,一度自分の強み,持ち物を再確認してみることが大切だなと思いました。」
「勉強をすることにおいて,一番大切なことは「楽しく」学ぶことだとわかった。英語を学ぶことは大学入試のためなど将来の保証のためではなく,自分自身の可能性を広げるためのものであると再認識できた。」
佐藤 裕崇 先生,貴重な講演を本当にありがとうございました。
佐藤教授のHP(Hirotaka Sato Group) https://hirosatontu.wordpress.com/
講演会の様子 南洋理工大学(NTU)写真 Wikipediaより
2025-01-15T10:37:24+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
2025-02-10T09:41:25+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
2月7日(水)に本校中学生と高校1・2年次生を中心に「未来創造プロジェクト」成果発表会を実施しました。午前中に全体会として、高校の部を北アリーナで、中学校の部を大講義室でそれぞれ実施しました。高校の部では、タイの海外連携協力校であるタイ・ノーンヒンウィッタヤコム校とZOOMで繋ぎ、学校紹介・研究発表・質疑応答をすべて英語で行いました。次に、全国高校生フォーラム2023に参加したグループも研究発表・質疑応答をすべて英語で行いました。続いて、中学3年代表の二つのグループ、高校代表発表として、令和5年度山形県探究型学習課題研究発表会で入賞した2つのグループ、そして、高校1・2年沖縄・西表フィールドワーク活動報告を、スライドを用いて行いました。中学校の部は各学年の代表グループによる口頭発表と高校2年による2つの代表班による口頭発表を行いました。昼食後は、中学校1~3年生と高校2年次生の研究発表を行い、質疑応答を通してお互いに学びを深め合いました。また、研究アドバイザーとして、山形県立保健医療大学保健医療学部遠藤恵子教授、他校や本校の先生方など多くの先生方に生徒たちの研究をご覧いただき、様々なアドバイスを頂きました。さらに、本年度は保護者の皆様もコロナ禍前と同様に参加することができるようになり、多くの参観者にご出席いただきました。今後、高校2年次生は、これまで行ってきた研究について日本語論文の作成を行ってから、英語論文の作成へとつなげていく予定です。
2025-02-10T10:19:45+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
2月9日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の後期第7回校内視聴を実施しました。今回は「トップアスリートの食事の秘密」と題し,寺田 新 先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生が2名,2年生が1名,3年生が2名,高校1年次44名が大講義室で視聴しました。「運動・トレーニングだけでなく,食事・栄養も同じくらい大切なんだなと思った。この時期の私たちは体重などを気にしてしまい,トレーニング量を増やして食事をおろそかにしてしまいがちだけど,疎かにしてしまうと,トレーニング効果を最大限に高められないということもわかった。また、サプリメントやプロテインに頼ってタンパク質を摂取しがちだけど,食品から摂取した方がタンパク質以外の栄養素まで摂取することができるから効率がいいのだな,と感じた。」(中学3年Iさん)」や「糖質や脂質はどこで貯蔵しているのか,どのような運動時に使われるのかを知ることができて良かったです。普段から糖質をしっかり摂取することを家族に教えたいです」(高校1年Kさん)といった感想のように,トップアスリートが実践している食事法の秘密・効果を解明する研究から多くのことを学ぶことができた講座でした。
今回の講座で今年度の「高校生と大学生のための金曜特別講座」は終了になります。来年度も開講を予定していますので,興味のある研究分野の際にはぜひ参加しましょう。
2025-01-16T08:31:26+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
2024-12-25T12:14:56+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
2月4日(日)に開催されたThe Alps Cup2024(甲信越ブロック主催オンライン英語ディベート大会)に本校ESS部が初めて参加しました。HEnDA(全国高校英語ディベート連盟)の全国大会と同様の準備型のディベート大会で、1年生を主体とした初心者対象大会と位置付けられています。もっとも、北海道から鹿児島まで全28チームのうち、全国大会常連のチームが過半数を占めている決して低いレベルではない大会です。本校のESSは中学3年生の早期入部メンバーと一緒に準備を進めて臨んだ1年生6名が4試合を戦い、今回の論題である”Japan should ban elderly people at the age of 75 and above from driving a car (日本は75歳以上の高齢者の自動車運転を禁止すべきだ)”について、コンパクト・シティや農業の面からアプローチする興味深い議論を進めました。結果的に3勝1敗(6位)で、強豪校にも勝つことができ、貴重な経験となったのはもちろん、縄優颯さんが得票数1位でベストディベーターに選出されました。この経験を来年度の県大会、全国大会に活かせるよう、さらに高いレベルのディベート技術を身につけていきます。
2025-02-07T11:59:57+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
2月2日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の後期第6回校内視聴を実施しました。今回は「光と電子の顕微鏡:速くて小さいモノをどうやってみるか?」と題し,石坂 香子先生(東京大学 工学部 物理工学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生が5名,2年生が1名,高校1年次23名が大講義室で視聴しました。「解析限界という言葉を初めて聞いて,今物理の授業で習っている波との関連性も考えながら話を聞けた。電子は一粒で波であり,粒であるという言葉が印象深い」(高校1年Aさん)」といった感想のように,物質科学の最前線にも触れる貴重な機会となりました。次回は2月9日の「トップアスリートの食事の秘密」となります。
2025-01-16T11:49:44+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校
令和6年1月26日㈮、27日㈯、秋田県秋田市にぎわい交流館AUを会場にして令和5年度東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会が開催されました。本校から高校2年次の4人が参加し、探究活動の成果を発表してきました。
1日目は3階の多目的ホールで口頭発表をおこないました。参加16校から発表がありました。本校生は10番目に「セイタカアワダチソウの持つ毒性に
2日目は2階展示ホールでポスターセッションを行いました。参加16校から28のポスターセッションがありました。本校生は「身近な熱を直接電気に。~夢の発電の実現を目指して~」という題で作成したポスターの前で研究内容を説明しました。大勢の人が訪れる中、上手に説明していました。
今年度は口頭発表とポスターセッションの2分野で発表がおこなわれました。参加した4名は充実した発表をおこなう事ができました。
【生徒の感想】
東北のSSH校が集まっているだけあって、発表を一度聞いただけではなかなか理解できないような専門性の高いことを探究している所が多かった。7分という制限時間に入り切らないほど濃い内容の研究ばかりで、それでも質疑応答でうまく返しきれないことがあるなど、実験の試行回数や多角的な視点の重要性も再認識させられた。また、同じような内容の研究をしている班と知り合い、情報を交換できたことも良い経験になった。
東北サイエンスコミュニティを通して、たくさんの科学好きや研究活動に熱心な人と交流し合うことができた。他校の研究はテーマがとても興味深いだけでなく、研究方法や考察の仕方などがユニークなものが多くて、大きな衝撃を受けた。また、自分たちのポスター発表においては、他校の生徒の皆さんからの質問や大学から来てくださった先生方からのアドバイスなどをたくさんいただき、自分たちの研究への理解が更に深まった。新たな課題が見えてきて、今後の具体的な研究方針を定めることに繋がったと思う。今回のこの貴重な機会で新たに知ったことや研究について学んだことを、今後の自分たちの探究活動に活かしていきたい。
2025-01-15T10:39:29+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校